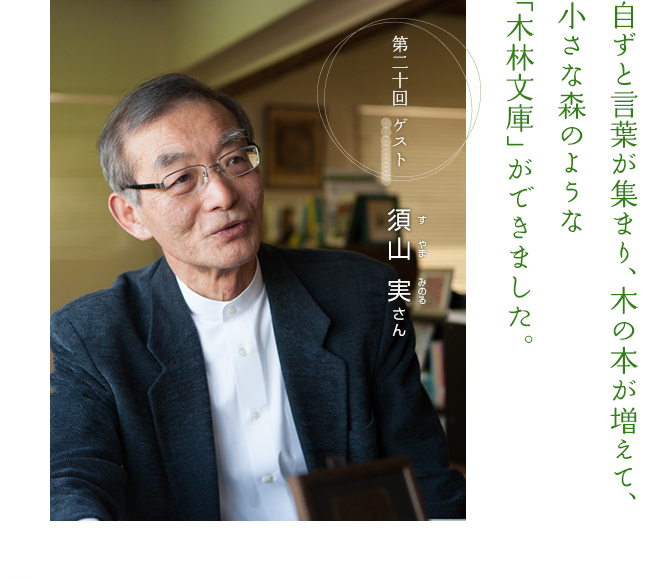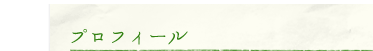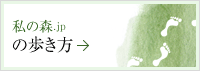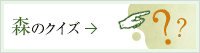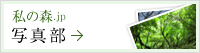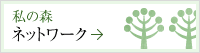東京・目黒の碑文谷公園の向かい側に子どもの頃から住んでいました。近所には100坪ぐらいの庭がある家が何軒かあって、小学生の頃はかくれんぼをしたり、カシやシイの大きな木に登ったり、アオキの赤い実を玉にしてパチンコをしたりして遊んでいました。木なんて特に意識しませんよね、小学生の頃は。だけど、木は庭にも周囲にも当たり前にあって、都会としては比較的多いほうだったと思います。

うちのすぐ近くには、周囲が400メートルぐらいある地主さんの森があって、そこも僕らの遊び場でした。柵も何もなく自由に出入りできて、奥には防空壕がそのまま残っていて、そこに入るのが冒険でしたね。
小学校の時は、その先の目黒通りを越えるのは「ちょっと遠いな」という感じで、向こう側に行くと一面キャベツとアブラナの畑。有名なサレジオ教会あたりも、当時はキャベツが多くて畑の匂いがしました。通りの向こうはモンシロチョウがいっぱいいて、「ちょっと田舎じゃん」(笑)っていう感じだったかな。

うちの庭には、農林省勤めだった祖父が少しずつ植えた木々が、外が見えないくらいにありました。カシ、シュロ、サクラ、カエデ、ツバキ、果樹では、カキ、ウメ、ナシ、イチジク、それに、祖父が「ポウポウ」と呼んでいたすごく香りのいい実がなる木があって、「これ、南洋の果物だよ」と言っていましたね。
カキの木は3本ありました。これは僕が『木林文庫』のエッセイの中にも書きましたが、ある朝、2階の窓から見たカキの木、その瑞々しい青葉があまりにも綺麗で、生まれて初めて「緑の輝き」を感じた。小学校4年生の頃だったでしょうか。それが、木とか緑を意識した初めての出来事だと思います。目の前に広がったやわらかな緑の輝きを、いまでも思い出します。
高校ぐらいから本を読むようになって、大学にはいってシュールレアリスムに出会いました。在学中は映画のグループに居て、そのあと、映画学校に2年ぐらい行きました。カメラもシナリオも全部をやらせる学校だったんですけどね、大島渚さんといっしょに仕事をしていた田村孟さんという方が随分丁寧に指導してくださって、「おまえは映画に向かない、書いたほうがいいよ」と言われました。その時はまだ出版ということは全然考えませんでしたが。

僕のなかでは、ポール・エリュアール、アンドレ・ブルトン、その二人の作品に描かれた場所に行きたいという気持ちが強くありました。また、プルーストの『失われた時を求めて』のイリエ・コンブレに住みたい、あの本のなかで「さんざしの匂いは、聖母の祭壇のまえにいるかと思えるほど、しっとりと、散らばらずに匂っていた。」と書かれた、あのサンザシを見るためにそこに行きたい……と思いがつのり、フランスへ渡りました。
パリに住んでみると、まずは四季を経験したいと思い、それからもうあと1年と、妻の仕送りを頼りに(笑)実質3年近く居ましたね。文学と映画の勉強をするにはうってつけの環境だったと思います。
東京に戻り、ご縁あって森関係の本を出している出版社に勤めました。「木」の本は担当しませんでしたが、編集の仕事のはじまりがそこでした。その後、僕が直接に木の本を編集したのは、平凡社のコロナブックスが最初でした。その時、なにか木の言葉を入れようということになり、タゴールのこんな言葉を選びました。
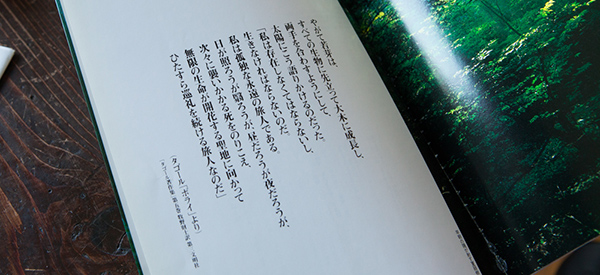
やがて若芽は、すべての生物に先立って大木に成長し、両手を合わすようにして、太陽にこう語りかけるのだった。
「私は存在しなくてはならないし、生きなければならないのだ。私は孤独な永遠の旅人である。日が照ろうが翳ろうが、昼だろうが夜だろうが。次々に襲いかかる死をのりこえ、無限の生命が開花する聖地に向かってひたすら巡礼を続ける旅人なのだ」
この言葉を気に入ったのが、たぶん後に『樹と言葉』という本をまとめるきっかけになったのではないかと、いまにして思います。
そのあと、ある企業の広報紙の編集で長田弘さんのページをつくることになり、ご相談にいったところ、長田さんが「木のページをつくろう」とおっしゃって。 第1回目には「アメイジング・ツリー」という素晴らしい詩を書いてくださった。長田さんは大学からずっと東京郊外にお住まいで、都会に住んでいる人の目で木と対話する、木が対話する相手として存在するという視線で書かれていました。

都会人は、そこここにパラパラとある木や、風や光や水を通して自然を感じるんですね。森というよりも「1本の木」を下から見上げて何かを感じるのだと思います。
『指輪物語』の中で、エルフ達が住んでいる巨大な木、マルローン樹を見上げるような描写が素晴らしくて、「ああ、こういう風に書けたらいいな」と思ったのを覚えています。僕が田園調布の公園でハナミズキを初めて見たとき、これを言葉にうつしたい、あの文章をまねできたらいいなあと思ったものです。
言葉にうつしたい。そう、木との関わりもブッキッシュなんですよね、僕は。
もちろん自然そのものと関わっているんだけど、どこかで、どうしても、たえず言葉に置き換えてしまう。もっと直接関わったほうが良いことはたくさんあって、そのために難しくもつまらなくもしていることがあるんだろうけど(笑)。
2010年に牧野富太郎植物園で開催された『樹と言葉展』に「木」の本を80冊展示したのがきっかけで、その後も木にまつわる本が増え続け、とうとう「木林文庫」という小さな図書室になりました。

木林文庫の木の本で一番数が多いのは、タイトルに「リンゴ」が入った本なんです。「リンゴのコーナー」には、世界中のリンゴの木にまつわる本があり、特に絵本は、30年近く前、長男と読むために買ったポーランド生まれの作家ヤノーシュの『おばけりんご』を筆頭にたくさん並んでいます。あとは、パリの書店で買った『Le Cidre(シードル)』という林檎酒の本もあれば、「囚われのリンゴ」という名前のお酒もあるらしい……。

いまは家族だけでやっていますけど、これからオープンにしていって、木の好きな人と本の好きな人が集まって、みんなでつくっていければいいなあと思っています。また、せっかくこういう場所がつくれたので、詩の朗読会やワークショップなどもやっていければと。
意識して集めたつもりもないのに、いつの間にか木の本がどこかにあったり、自ずと言葉が集まってできたのが木林文庫です。このごろは、「木」という字が気になり始めると「本」という字まで気になって(笑)。
「木林文庫」について

須山 実(すやま みのる)
エクリ主宰
1948年、東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、原宿学校映像クリエーター科、パリ第3大学で学ぶ。出版社、編集プロダクション勤務を経て、編集・出版事務所エクリを主宰。アルセーニイ・タルコフスキー(映画監督アンドレイ・タルコフスキーの父)詩集『白い、白い日』、ロベール・クートラス作品集『僕の夜』など、既存の枠にとらわれない独特な視点で出版活動をおこなっている。
2010年、エクリは高知県立牧野植物園で開催された「樹と言葉展」に併せて、『樹と言葉』を上梓した。この企画展には、エクリ所蔵の「木」の本を八十冊展示した。「木」を分解すると「八」と「十」になる。それ以降も「木」にまつわる本は増え続け、「木林(きりん)文庫」として小さな図書室となった。
生まれて以来東京都内目黒区に住んでいるが、家の庭には、農林省勤めだった祖父の植えた木々が多かった。柿、梅、桜、梨、樫、椿、楓、無花果、棕櫚、金木犀、そして関東には珍しい梛。沈丁花、つつじ、山茶花、紫陽花、茶、山吹などの潅木もあった。
線路をはさんで池を抱えた碑文谷公園があり、桜、ぶな、欅に季節ごとの味わいがある。また歩いて15分ほどのところにある林試の森の樟やスズカケの立ち姿は美しく、時折、会いに行く。